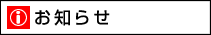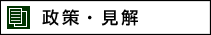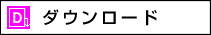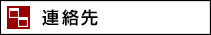大阪文壇事件簿9 川端康成③
「孤児根性」とは何か
入江 春行
『十六歳の日記』 についての疑問がなお二つある、 と前回の終りに書いたので、 まず、 それについての私見を述べたい。
「中央公論」読み自作登載を期待
一つはなぜ、 五月四日からか、 ということである。 これは、 その前日の日記に、 祖父のことを書いた 「小説の傑作」 が 『中央公論』 に載せられることを期待しているので、 十年後の今、 かえりみて気恥ずかしく思ったのだろう。 たしかにその頃の 『中央公論』 は十七歳の少女、 中條 (後の宮本) 百合子の小説 (『貧しき人々の群』) を載せる (一九一六〈大正五〉年九月号) など、 若人の登用に熱心だった。 それにしても、 中三で 『中央公論』 を読み、 自作の登載を期待するとは、 さすがに康成は早熟だった。
『十七歳の日記』 を 『十六歳の日記』 と改題したのは、 夏目漱石の 『こころ』 に触発されたのではないか、 というのが私見である。 『こころ』 の主人公は、 十六歳で孤児となり、 家屋敷、 田地田畑をすべて処分する。 康成の場合も、 墓以外はすべて処分した。 そういうことが 『こころ』 の主人公にあまりに似ていたので、 思わず 『十六歳』 としてしまったのではないか。 ふるさとへの思いを書いた 『父母への手紙』 に綴っている心情は 『こころ』 の下巻九章に述べられている主人公の心情と酷似している。
人々の顔色窺う「癖」に自己嫌悪
そして、 康成は 『こころ』 の主人公と同じように、 また、 前々回に述べたように 「孤児根性」 を抱いたまま上京した。 康成のいう 「孤児根性」 とは何か。 彼は 『日向ひなた』 という作品で 「人の顔をじろじろ見る癖―この癖に私は自己嫌悪を感じている。 幼くして親や家を失い、 他家の厄介になっていた頃、 人々の顔色ばかり読んでいたのではなかろうかと思うからである」 とみずから答えている。 また 「おばあさんがなくなって、 私は一層いじいじした子供になった」 ( 『祖母』) とも言っている。 一人息子 (つまり康成の父) に先立たれた祖父母、 特に祖母は孫の康成を溺愛したらしい。 『祖母』 に 「大きな屋敷に三人はかなり陰気に、 しかし気楽に暮らしていた」 と書いている。
祖母は康成が七歳の時に亡くなったので、 よく覚えているのは当然であるが、 驚くのは、 二歳六ヶ月で死別した母についても記憶があることである。 住吉大社の反橋を母に背負われて渡った記憶を書いている 『反橋そりばし』 という作品がそれである。 康成は記憶力抜群だったと言われるが、 さすがである。 今、 住吉大社の境内にはその作品の一部が文学碑となっている。
名誉市民の称号を贈られた康成
ふるさとについて 「中学生の頃の私は、 いずれ立身出世をして、 盗まれただけの墓のまわりを買い戻し、 立派な石垣の囲いでもしようと、 空想したものでありました」 ( 『父母への手紙』) とか 「親のない子の私をいたわってくれたふるさとはなつかしいが、 しかし無頼放浪の私は旅のところどころにも、 ふるさとを感じる」 ( 『私のふるさと』) などと述べているように、 必ずしも望郷一筋ではない康成に対して、 茨木市は、 はじめての名誉市民の称号を贈った。 もって瞑すべし、 と言いたいところであるが、 その推挙式で、 彼は他人の間で苦労しているだけに人をそらさない術を心得ているから、 そつなく深甚の謝意を表しつつも 「茨木は……少年時代を過ごしました故郷なのでありますが……今まであまり参りませんでした」 と言い 「必ずしも茨木市の名誉市民にふさわしいことを書くかどうかははなはだ疑問なのでございまして」 とやんわりと述べた。
市はまた 「川端康成文学館」 をも作った。
次は与謝野晶子のライバルと言われた女性をとりあげる。 (いりえ・はるゆき 元大谷女子大学教授)
投稿者 jcposaka : 2007年03月04日