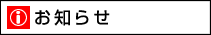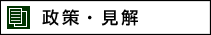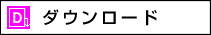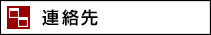編集長のわくわくインタビュー 作家・旭爪あかねさん
『稲の旋律』で伝えたかったことは?
『引きこもったから今がある
 今冬完成予定の映画 『アンダンテ〜稲の旋律〜』 (金田敬監督) が5月にクランクイン。 大阪でも上映を成功させる運動が始まっています。 講演で関西を訪れた原作者の旭爪あかねさんに、 小説が生まれたきっかけや、 作品への思いなどを聞きました。 (聞き手 佐藤圭子編集長)
今冬完成予定の映画 『アンダンテ〜稲の旋律〜』 (金田敬監督) が5月にクランクイン。 大阪でも上映を成功させる運動が始まっています。 講演で関西を訪れた原作者の旭爪あかねさんに、 小説が生まれたきっかけや、 作品への思いなどを聞きました。 (聞き手 佐藤圭子編集長)
『稲の旋律』 は、 「しんぶん赤旗」 連載中から話題を呼び、 東京芸術座などいくつかの劇団がお芝居にもされて、 私も4年前に大阪の劇団きづがわの舞台を見ました。 今度は映画になるということですが。
旭爪 本当に光栄で、 うれしいです。 舞台化していただいた時もそうでしたが、 一人でちょこちょこ書いた小説をこんなに大勢の人が時間をかけて、 また別の作品に作り直してくださることは、 全身全霊を傾けて批評をしていただいている感じがして、 なんてぜいたくなことなんだろうって。
『稲の旋律』 には、 あかねさんご自身の体験が投影されていると聞きましたが。
引きこもりの自分と重ねて
旭爪 この作品を書いたころというのは、 引きこもって職場に行けなくなって、 休職した揚げ句に職場を辞めてしばらくした時だったんです。 実家に居て何もせず、 まだ対人緊張があったし、 引きこもりから抜け出しかけているという、 主人公の千華より半歩先を歩いているような感じでした。
稲と音楽という発想はどんなところから生まれたんですか?
旭爪 引きこもっていた時に、 よく自宅近くの田んぼの周りを散歩していました。 風に揺れている稲を見ていると、 その風が自分の心をわたっていくようで、 私でもまだ生きてていいんだ、 まだ何かできることがあるかも知れないと思えたんです。
それでその風景の美しさを言葉にしたい、 稲とピアノの出てくる小説を書きたいと思って、 農業高校に通う男の子がピアノの上手な女の子に恋をするという他愛ないラブストーリーを書きました。 ところが合評会で、 「農業というのはもっとどろくさくて、 苦しいものなんだ」 「作者は農業のことが全然分かっていない」 とみんなから批判されて。 すごくショックだったんですが、 当たっているなと思って、 1994年に千葉県の農業青年たちがやっている米作り教室に通い始めました。 茨城県の酪農家の方にも出会い、 2001年にやっと書いたのが 『稲の旋律』 でした。
自然や生き物を相手にする農業というのは、 自分の思い通りにことが進まず、 台風で稲が全滅したり、 天候によって作業が延期になったりするんですね。 そういう体験が身に染みている農家の人たちというのは、 お天道様を恨んでもしょうがないから、 また明日やろうというように気長に対応しておられる感じがしました。
気長に待つ姿勢に救われた
そして人間に対しても、 あなたはこうしなさいなど枠にはめたりしないで、 その人らしくできるように、 信じて任せて待ってあげようと接してくれている気がして、 そんな中でずいぶん私も救われたと思います。
そんな貴重な体験を通じて書かれたのが 『稲の旋律』 だったんですね。
旭爪 『稲の旋律』 の前までは、 何で引きこもったのかを考える小説を書いていました。 それを書かないと、 これ以上一歩も進めない気がして、 書くことで何かを突き破って前に進みたいという思いでした。
ところが 『稲の旋律』 の時はちょっとそれまでとは違って、 自分が引きこもっていた時に感じたこととか、 周りで支えてくれた人によって気付かされたこととか、 そういうことを自分と同じように悩んでいる人たちに伝えたいという気持ちが強かったんですね。
『稲の旋律』 を書いた後、 千華のその後をすぐ書きたかったんですが、 自分と千華があまりにも近くて、 いまの時点では千華のその後はとても書けないと思いました。 そしたら千華や自分とは違って、 引きこもらないで社会に出ることができた若い人たちの人生を追体験してみよう。 彼らと自分たちとの共通点や共有できるものが見つかったら、 千華や自分がこれから社会に出て行く上でのヒントが見つかるかも知れないと思って、 若い人に話を聞かせてもらって書いたのが 『風車の見える丘』 だったんです。
なるほど。
旭爪 そんな風に作品によって気持ちがちょっとずつ違うんですが、 基本的に私は書いて考えて、書き終わった時に、 書く前とは違う自分になっているような作品を書けたらいいなと。 なかなかそうはいかないんですが。
ご自身の体験を通して、 あらためて感じておられることや、 いまもなお引きこもりや人間関係などで悩んでおられる人へのメッセージがあれば。
自分も大事に感じられない
旭爪 私が引きこもっていた時は自分に全然自信や誇りが持てなくて、 自分のことを大切に思えませんでした。いま、他者に対して破滅的な行動に走ってしまう人たちを見ていて、 相手だけでなく、 自分も大事に感じられない状況にあるのではないかと思うと、 引きこもっていた時の自分と紙一重の隔たりしかないんじゃないかと感じるんです。
私の場合は、 小説を書くことと、 書いたものを仲間同士で読み合って批評する場を持てたことで、 自分自身が引きこもりから少しずつ抜け出してこられたような気がします。
合評会に参加する前の私は人に対しすごく気を使って、 当たり障りのないことをいつも言って自分を取りつくろっていました。 それで気疲れして対人恐怖みたいになっていたんですが、 小説を書いて批評し合うということをやってみると、 自分の小説に対して思ったことを言ってほしいという気持ちから、 自分も相手に対して率直な意見を言わなきゃいけないという状況に立たされていきました。
それで、 いいことも悪いことも率直に、 でも相手を傷付けないように優しい言葉で言う訓練みたいな体験をして、 たとえぎくしゃくとした人間関係ができても、 またよく話し合えば乗り越えられることや、 対等で親密な人間関係の築き方みたいなものも学んで、 何でも話し合える友達もできました。
それまでは、 他人というのは自分を評価する存在で、 人から評価されない自分は価値がないと思ってきたけど、 評価されようがされまいが、 いまの自分がいとおしいと思えるようになりました。
壊れる寸前で守ってくれた
私自身、 引きこもらないで済めば引きこもりたくなかったと思います。 でも引きこもらなかったら、 いまの年になってこのように自由に、 楽にはなれなかった。 よく、 引きこもりをどうやって克服したかと聞かれるんですが、 引きこもりというのは敵対視するものではなく、 むしろ壊れる寸前で自分を守ってくれた、 苦しかったけれども考える時間も、 やり直す時間も与えてくれた、 味方に近い存在でした。
引きこもりは、 時期がくると、 ポロっとそこから抜け出したり 「卒業」 したりするものなのではないか、 という気がします。 もし本当に自分がそういう状態から離れたいと思っていたら、 周囲の人たちの理解と協力があれば、 いつか必ず離れられる時がくると思います。
『アンダンテ〜稲の旋律〜』 の物語 藪崎千華は幼いころから音楽の道を歩むが、 激しい競争の中で自信を無くし登校拒否に。 大学中退後もアルバイト生活で人間関係がうまくつくれず、 家に閉じこもり、 絶えず両親と衝突する。 そんなある日、 千華は、 「誰か私を助けてください」 と書いた紙をペットボトルに詰め、 千葉県の水田に置いて帰る。 それを拾った広瀬晋平との交流が始まり、 千華の引きこもり生活が変化していく―。
ひのつめ・あかね 1966年、 東京都生まれ。 宇都宮大学農学部卒業。 97年、 『冷たい夏』 で第2回民主文学新人賞を受賞。 「しんぶん赤旗」 で連載した 『稲の旋律』 で、 引きこもりの女性が農業従事者の男性らとの交流を通して成長する姿を描き、 第35回多喜二・百合子賞を受賞。 日本民主主義文学会会員。
投稿者 jcposaka : 2009年06月25日